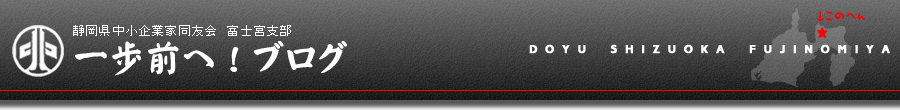富士宮市中小企業大学09 第三講報告 「日本文学の系譜」
平成21年度 富士宮中小企業大学 第三講
■開講日:平成21年10月13日(火)
「日本文学の系譜」 夏目漱石から村上春樹に至るまで
講師 静岡大学人文学部 准教授 森本隆子氏
文学とは、古典においては「ミメーシス論」により、現実の模倣であり、真理の再現を追及することであった。
しかし、「カルチュアル・スタディーズ派」の登場により、代表的名作は真理なのかと言う疑念が生じた。アルフォンス・ドーデの「最後の授業」においては、教師のフランス語での最後の授業を感動的に語っているが、舞台であるアルザス地方にはアルザス語があり、教師はフランス語を浸透できなかったことを悔いている。
名作といわれる本の中には「ミメーシス」ではなく、「社会システム」と「自己」との葛藤(時代への批評)が描かれている。そのような観点から、夏目漱石と村上春樹を改めて読んでみよう。
「坊っちゃん」において漱石は、忠孝一本の「家族主義国家観」における、長男の圧倒的権力(金力)に対する次男坊の悲哀、そして長男との学歴差による家族内での疎外感を描き。四国に渡ってからは、「赤シャツ」を代表とした近代資本主義者(金で全てを解決する)と対峙する没落士族「うらなり」や、金銭の授受が形成していく不浄のネットワークに対する怒り。その世界から乖離した純粋な美しさの象徴「マドンナ」への憧憬と恐れ(欲望)等に翻弄される「坊っちゃん」。不浄の地を離れ、無償の愛の象徴である「清」の元へ教職をなげうって東京へ帰る。しかし「赤シャツ」と「坊っちゃん」は漱石の二つの自画像ではなかったのか。
「こころ」においては、叔父の裏切りに「金を見ると、どんな君子もすぐ悪人になる」と金銭欲を嫌悪し、その対極に異性に対する恋愛をおいて昇華した。しかしその恋もKというライバルへの嫉妬であったことに気づく。Kの死を孤独感からと理解したとき、自らも同じ道を辿ることになる。しかし「先生」と妻との絆、「先生」と先生の遺書(妻への秘密)を受け取った「私」との絆、どちらが強いのだろう。いずれにせよ永遠の恋愛は永遠に結ばれない関係にしか成り立たないのである。
村上春樹の「ノルウェイの森」では、「僕」が作り出した「僕自身」にしか行き着かない世界を描いている。「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」。 「歪み」に順応できないものは死を選び、現実社会(生者)は醜い世界である。20歳頃死んでしまった者たちに自己投影し、全く閉じた自分だけの純粋な空間を作り出し、現実の社会関係から逃避している。回想期限の1968年とは近世から現代に、世界的にも大きな変換点であった。
村上ワールドのアイデンティティはこの時代への反発ではないだろうか。
報告:シンコーラミ工業株式会社 代表取締役 河原崎信幸