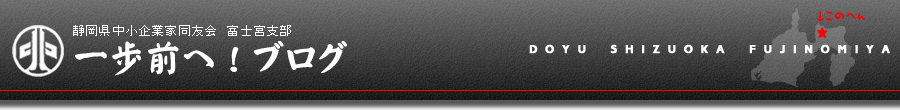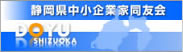9月6日(金)、志ほ川バイパス店にて9月度支部例会が開催されました。
参加者:会員42名、他支部会員4名、オブザーバー3名、事務局1名、計50名
報告者 ㈱大五堂 深沢文具 専務 深澤哲郎氏
NPO法人 母力向上委員会 代表理事 塩川祐子氏
㈱富士一商会 代表取締役 外木昌宏氏
以上 3名
通常2月・3月の二回に分けて開催していた、「新会員さん、出番ですよ!」でありますが、今年度からの試みとして、前期・後期に分け、9月(前期)3月(後期)での開催と致しました。

今回は、その前期として、3名の報告者に各20分の持ち時間の中で、自己の生い立ちから現在に至るまでの経緯、現在抱えている悩み・同友会に対する思いについての報告してもらいました。
深沢文具 深澤氏
深沢文具の創業は1910年(明治43年)来年には創業110年を迎える老舗文具店であります。その歩みとともに、自身の経歴・思いを語ってくれました。

経営理念 「人が喜び自らも喜ぶ。この仕事の追及に幸せがある。」
深澤氏はS46年生まれ48歳。物怖じせずに行動できるタイプで、「やってだめなら変えてみましょう」と大雑把な部分も持ち合わせていると、自己を分析している。
学生時代から接客・販売のアルバイトを経験。また、バブル崩壊により、早めの就職活動を始めることに。当時は、とりわけ何になりたいというわけでもなく、家の仕事を継ぐことも全く考えていなかったが、強いて言えば、パソコンを使った仕事をしてみたいと思い、SEの職に就くことを決める。
就職して2年ほど経った頃、親からの電話で、「自営の業務を拡大するにあたり、どうせ仕事をするならうちでやらないか?」と、誘いがあり、内容は、「得意先の業務拡大に伴い、人手不足やパソコンを使ってのデータのやり取りが増えたこと」で、深澤氏が必要であるとのことでした。それを機に、ある文具メーカーの勧めで、東京の大手文具店に転職し、修業をすることに。この修業時代が自分の人生において、多大な影響を与えることになる。
数年の修業時代を経て、結婚後、30歳を過ぎた頃、今の深沢文具に入社。現在18年目を迎える。リーマンショック後、数年経ったころから大型店の吸収合併に拍車がかかり、当時の主な客先が、次々とその影響からか消えていき、最後は最大手の客先までも失うというどん底を味わうことになる。現在も厳しい中ではあるが、小口の客先から官公庁に至るまでカバーし、積極的に営業を行っているところである。
そんな中、同友会と出会い2017年入会。入会時はマイナスからのスタート。例会をはじめとする様々な会合を通じ、先輩方・仲間から刺激やヒントを得て、よい経営環境の構築を目指す。また、来年110周年を迎えるにあたり、代表取締役に就任予定。
NPO法人 母力向上委員会 塩川氏
~生まれてきてよかったと思うことができる人生に~
2008年 妊娠・出産・子育てをプラスに、お母さんによる、お母さんの為の、お母さん支援学校してきた市民団体が発祥。2015年活動の幅を広げるために、NPO法人化し、現在に至り、現在4期目。総勢52名のスタッフの元運営を行っている。個人の賛助会員・法人の賛助会員の賛助金、市の委託事業費等が主な収入源でとし、妊婦・子育て始動時の母親をターゲットに、講座・イベント・情報発信等の支援活動をしている。
塩川氏本人は、その育った家庭環境から、祖母・母親の背中を見てきたことで、「女性の活躍」のなんたるか、大切さを思い知る幼少期であったそうであり、それが今につながっているのだと振り返る。趣味は「人間観察」特技は「妄想」と、人間の心理を探ることに興味を抱く。中学・高校とバレーボール部に所属し、そこでけがの手当てをすることにより、看護師を目指すこととなり、地元の看護大に進む。大学の運営元の影響か、「利他の精神」と「困難を克服し、事業を開拓していく姿」を学んだことが、今の母力向上委員会につながっている。

地元の総合病院に就職後、脳神経外科・救急科を志願し激務の新人時代を過ごす。この時の命たちから学んだことが、自身の人生のテーマとなり、現活動の源になる。
26歳の時に結婚。32歳の3女の出産を機に母力向上委員会が誕生。自身の結婚・出産・子育てが多分に影響をしている。
立ち上げ当時(2008年)、同じ立場の母親声を聴き、その生の声を関係機関に届ける必要性を感じ、地域密着型のフリーペーパー「うみだす」を発行。その後、活動の幅を増やしていく中で、NPO法人化していく必要性を感じる。そんな問いかけの中で、スタッフの反対にあったりと、紆余曲折もありながら、2015年法人化を果たし、本職となる。
法人化当時は、今まで経験もしたこともない金額を動かすことへの戸惑い、税金を使って失敗するわけにはいかないというプレッシャーに苛まれる日々。メンバーに対し自覚をもって行動してもらうべく、その思いを伝えることにも苦心することに。
自分に足りないものは何だろう?そう問いかける日々の中で同友会と出会い、オブザーバー参加をする。理念が大事であることを学び、社会でなくてはならない存在になりえるのか?その答えを求めるため、入会することを決断。
2018年4月、拠点を変え心機一転頑張っているところです。
同友会の皆さん、どうかいろいろ教えてください!
㈱富士一商会 外木氏
富士一商会は、昭和22年自転車の仕入・販売を生業にして創業。
現在、従業員9名。
業務内容は、自転車・オートパーツ・電動四輪車等の卸し。静岡県東部・中部・山梨県の一部にをカバーしています。
<経営理念>
・一人一人が個性を発揮して生き生きと働くことができる会社を目指す
・全員が協同して、関わる人たち、取引先、周囲との絆を深め、その和が社会の潮流となって広がっていくことを目指す
・高次元の人間を目指し、日々進歩する
外木氏は、大学卒業後、1996年東京の大手スーパーに就職。
2002年5月に 現在の富士一商会に入社。
二輪業界の動向として、市場規模は縮小傾向。更に国内メーカーも、中国のOEMが9割とその業態も変化し、更に御多分に漏れず、量販店の台頭により業態も厳しい状況に置かれております。

入社後、父親の入院や、ベテラン社員を含めた退職者の続出と、試練を迎えることになる。
現在、倉庫の空いたスペースを利用した修理事業の立ち上げを検討する一方。富士宮という土地柄上、坂道が多いということによる電動自転車の需要見込みを期待した事業展開を考えている。それには、異業種とのマッチングや、役所への働きかけが必要とされる。
今後の課題として、倉庫の活用、もう一つの柱を立てることになるのですが、それにはどうしたらいいのか?そんなヒントがもらえるのではないかと、同友会に入会することに。
同友会から、色々な経験と知識を学びたい。そして、今苦境に立たされている、自社の経営に落とし込みたいと考えている。
報告者3名、皆それぞれの悩みを抱え、その解決策を模索する中で同友会と出会い入会。
誰とて、順風満帆な状況ではありません。会員全てが、悩み苦しむ状況の中、そのヒントを求め、お互い高めあい、決して卑下することなく困難に立ち向かっています。その仲間として、富士宮支部の辞書に、新たな3ページが追加されました。
7月24日(水)、愛知同友会 西三河支部 碧南・高浜地区7月度例会に、(株)アサギリ 簑威賴氏が報告者として登壇するとのことで、富士宮支部から7名の会員が地区例会に参加致しました。
参加者 阿久澤、伊藤、稲原、宇佐美、穂坂、簑、渡辺(一)

報告タイトルは「 Your Company Happy? ~ 経営理念ってあったほうが良いよね ~ 」で、全国大会で簑氏と同じテーブルになった地区の会員が、経営理念に真摯に向き合う簑氏の姿勢に大きな感銘を受け、「経営理念を語ってもらうなら、簑さんで」という強い想いで実現した地区例会でした。
西三河支部 碧南・高浜地区は、会員110名を有し、毎月の地区例会参加者が80名を超えるという全国的にも大変稀有な地区(支部)であります。さらに今回は、特別例会ということで、当日は、ゲスト・オブザーバーを含めて、120名を超えるエントリーがありました。

広い会場に、20近いテーブルが並ぶ姿は、まさに圧巻の一言。静岡では、なかなか見られない光景に、富士宮支部会員のテンションも上がります。
簑氏の報告は、「たゆたえども沈まず」という経営理念を地で行くような、波乱万丈の出来事を振り返りながら、その場その場でいかに経営理念に救われたかを語る、正に理念経営の実践そのものの「我が経営を語る」でした。

特に、金融機関が融資の可否を判断する際に作成する事業性評価シートの記入項目のトップに経営理念があり、経営理念を持たない会社・経営者にとっては、トップ項目が空欄=融資対象にはならない、ということであることと、コンプライアンスに厳しい企業ほど、取引先の経営理念に着目し、それを確実に実践しているかを企業訪問時に確認している、という2点の実例を挙げて、「理念が要るか要らないかではなく、理念がマストの時代になった」ことを強調していました。

バズテーマは「経営指針は必要と思いますか?」でした。こういうYesNo形式のテーマだと、Noと考える方の意見をYesに持っていくことが難しく、意見が二つに分かれたままで、時間オーバーとなることがどうしても多くなってしまいます。
実際、自分が座ったテーブルでも、Yes4名・No3名に分かれてしまい、Noの方が積極的に意見を言ったことや、グループ討論の時間が30分と短かったこともあり、良い方向にグループ討論を進ませることが出来ませんでした。(グループ長も四苦八苦していました)
「学び方を学ぶ」と良く言いますが、企画された例会の意図を考えて、自分のポリシーというフィルター外し、「まずは吸収する」という姿勢が改めて必要であることを感じました。

最後に、参加オブザーバーからの感想、他地区ゲストからの連絡をする時間がありましたが、あれだけ大勢の人数を短時間で捌くスムーズな運営を見て、参考にしたいと思いました。
大変貴重な経験をすることが出来ました。この経験を今後の支部例会運営に還元していきたいと思います。
7月16日(火)、富士宮清掃(有)会議室にて、第1回(仮称)流通・小売部会が開催されました。
参加者:赤池、阿久澤、稲原、宇佐美、遠藤(嵩)、大澤、河村、草ケ谷、佐野(充)、塩川(拳)、竹内、外木、西躰、細野、深澤、宮下、望月(俊)、望月(知)、望月(史)、渡邉(昭)、渡辺(一)、渡邉(卓) 合計:22名
これは、厳しい状況に晒されている流通・小売関係の会員が集まって、どうしたらこの状況を打開出来るのかを定期的に討議する場として、今回新しく発足した会議体です。
支部長挨拶、部会の趣旨説明をした後、一人2分程で自己紹介と自社を取り巻く現況、この部会への参加動機を発表してもらいました。
どの会員も「売上げをつくる」ことに四苦八苦している現況が、改めてはっきりと浮き彫りにされました。
自己紹介の後、流通を主体とするグループと、小売を主体とするグループの二つに分かれて、グループ討論でさらに深堀りを行ないました。

予定の時間を大幅にオーバーしてグループ討論が行なわれ、流通・小売共通の問題としては、これからますます加速化する人口減少社会によるパイの縮小と、異業種参入による競争の激化の2点が挙げられました。
小売グループのまとめとしては、大企業の進出とインターネットによって、苦しい戦いを強いられていること、特に、インターネットがあらゆる面で大きな影響を及ぼしていることが報告されました。
流通グループのまとめとしては、大企業の進出によって立ちいかなくなった小売店がどんどん廃業をしていることと、大企業の囲い込み(発注が地元中小企業から大企業のグループ企業へ)が進んでいることの2点により、売り先を失っていることが報告されました。
最後に、竹内昭八氏より、「単に商品を仕入れて得意先に納品するだけの形態では、生き残ることは不可能な時代になっている。売り手にも買い手にも価値のある取引をどう構築し、地域で必要とされる企業となるために、ここで議論を尽くし、自らの頭で考え、行動し、協業し、前を見て進むしかない」というまとめで、第1回目の部会が終了しました。
次回は、より具体的な課題で議論を深めていきたいと思います。
7月12日(金)、志ほ川バイパス店にて7月度支部例会が開催されました。
参加者 支部会員:45名、オブザーバー:2名、事務局:1名、合計:48名
報告者は、鈴木産業(株) 鈴木昭二郎代表取締役社長で、支部独自組織の経営指針研究会で2年の歳月を掛けて生み出した経営理念を中心に「我が経営」を語って頂きました。タイトルは、「フジマーク」に出会えて良かったね。~指針成文化の道のりでの気付き、実践での気付き~です。

鈴木産業(株)は、昭和12年に祖父である鈴木徳一氏が始めた作業用手袋の製造が始まりです。昭和40年に法人化後、昭和43年、祖父の急逝に伴い、父親である孝昌氏が後を継ぎます。
翌昭和44年に昭二郎氏が生まれましたが、自宅に隣接する工場で縫製作業を行なっていた影響からか、小さい頃から喘息に悩まされてきました。高校に入学し「このままではいけない」と一念発起し、空手で自分の体を鍛え、黒帯取得とともに喘息を克服します。
大学卒業後、1年半の語学留学を経て、関連企業の営業職に就き、そこで大活躍。5年後、約束通りに鈴木産業に入社し、様々な部署を経験する中で自身の能力を遺憾なく発揮。業界トップに近いところまで会社が成長します。
さらなる成長をと目論んで、中国から製品を仕入れるようになったところ、不良品が多発し、取引先を幾つも失うことに。また、そのクレーム対応に疲れた社員が、何人も会社から去っていくという悪循環に陥ります。
「安かろう悪かろう」からの脱却を目指し、新たに立ち上げた商品部で自ら部長を務め、日々商品の品質向上を目指すものの、業績は一向に上向かない。そんな悩みを抱えているなかで、平成24年、同友会に入会。

会での学びを深めていくなかで経営理念の重要性に気づき、経営指針研究会に参加。ここで2年近くの時間を費やし、経営理念を創り上げます。
理念を作成するなかで自社の強みに気づき、それを生かした新規事業「倉庫業」に取り組んだ成果も、ようやく出始めるようになりました。

昨年12月に新社長に就任し、創業者鈴木徳一氏の精神と、自身も同友会の会員として作成した鈴木孝昌会長の経営理念を包み込んだ、鈴木昭二郎氏の想いの詰まった経営理念を社員全員の前で発表しました。
社内の隅々にまで理念が浸透するには、まだまだこれから時間は掛かるのでしょうが、理念に共感する社員の輪が少しずつ広がっているのを実感しているとのこと。
同じ方向を向く社員を増やすことで商品開発力・商品企画力を高めて、オリジナルブランドである「フジマーク」商品をどんどん世に送り出したいとの決意の発表で報告は終了しました。

グループ討論テーマは「自分の想いをどのように社内に浸透させますか?」でした。グループ発表では「○○という方法で社員と理念を共有しています」というようなテクニカル論を発表するグループはほとんどなく、何故浸透しないかの原因を深堀りしたり、経営理念の重要性を改めて考え直したり、浸透した先にどんな変化が出るのかを考えたりとバラエティーに富んだ発表となりました。
「経営理念が持つ力」について、改めて考え直す切っ掛けになった例会となりました。