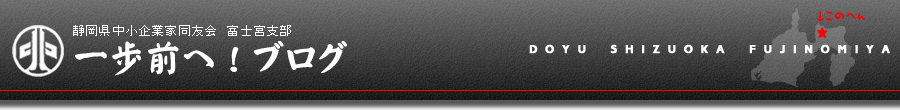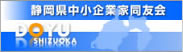富士宮支部2月の例会は、『地域金融の未来と中小企業の関係』
~自社事業の見える化で金融機関・支援機関と対話し、共通価値の創造へ~ということで、
一般社団法人 日本金融人材育成協会 会長 森 俊彦氏の講演を聞かせていただきました。
経営デザインシート・ローカルベンチマーク(略してロカベン)・金融機関は中小企業と伴走する
金融リテラシーはトップに必要・金融機関の選択と付き合い方・お金の借り方
お金は血液・日銀は心臓・血管は金融機関等、わたしにとってはとても頭の痛いお話でした…
また、中小企業の年齢層 平均70歳、借入金債務保証の引継ぎはそれ以外の多くの経営者の課題であり、
廃業問題の背景の一つ等、私の会社ではまさにその通りの状態であり考えさせられました。
今後はわたしも金融機関と上手く付き合えるようローカルベンチマークを金融機関と一緒に
作れるよう、森氏のお言葉の実践しないとはじまらないという事で、即実践していけるようにしたいです。
報告:Eグループ 村上亮介
富士宮支部7月の例会は、「年中夢求~世界一の豚博士が夢見る50年先の未来への挑戦~」ということで、富士農場サービス 代表理事 桑原康氏の報告を聞かせていただきました。
理念は、消費者に喜ばれる豚を作るということで、豚への愛、仕事への情熱がとても感じられるお話でした。
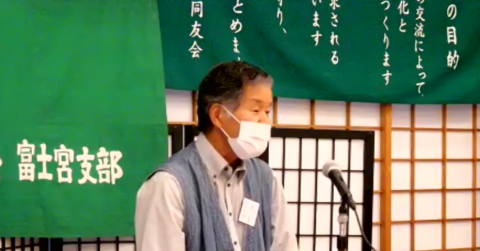
自分自身、豚のおいしさは、飼料や水や飼育環境で決まるものだと思ってましたが、なんと50%は原種で決まるということを知り驚きました。話を聞くまでは、人工授精サービス業についてピンとこなかったのですが、それがいかに重要な事なのか改めて知るとともに、凄い仕事をされている方がこの街にいるんだなと思いました。
これから豚を食べるときには、どのような豚なのか気をつけてみてみます。

豚熱や豚コレラに左右されてしまう経営の御苦労のお話がありましたが、ずっとそういったものとの戦いがあるということで、今のコロナ渦にお話をきいたので、その大変さがより感じられました。また、マイクロ豚の開発による医療貢献もされているということで、幅広い分野にまで御自身の仕事が関わっているといことは本当に凄い事だと実感しました。

今回会場である志ほ川バイパス店さんでは、地下にもネットを引き、サテライト会場も設営しました。
コロナ禍の中、適度に距離を保ちながら多くの方に参加できるような環境づくりも引き続き行っていきます。
報告:Eグループ 渡辺陽介
令和3年3月19日金曜日
今年度最後となる3月度例会は「新会員さん出番ですよ!」と題し、zoomと合わせたハイブリッド例会として、志ほ川バイパス店にて開催されました。
毎年この例会は、新会員さんが自分をさらけ出し、富士宮支部の新たな辞書の1ページとなっていく登龍門でもあります。今回も3名が報告を済ませ、支部の辞書が厚みを増すこととなりました。

1人目は「宮崎ふとん店 宮崎哲也氏」
宮崎氏は「あきらめが悪い私です」と題し、3つのターニングポイントにおいて、自分の人生がどのように変遷してきたのかについての報告でした。
① 数学者としての夢に向かって走り続けた青年時代
② 社会人として基礎を叩き込まれた塾講師時代
③ 婿入りして寝具店・山小屋経営を営む現在
夫々に辿ってきた経験は違えど、本質を極めようとする気持ちから、「メーカーのものを売っているだけでいいのか?」との疑念にとらわれ、自社のオリジナル商品として、オーダーメイドの快眠枕の販売を手掛けることとなります。その姿は、研究者としての土台があったからこそ今に活きているのではないかと思われます。
「小売りからメーカーへ 世界のMIYAZAKIブランドへ」
この10年ビジョンに向けて、同友会活動で得ていく知識・経験が、更なる進化へ向け、活かされていくと思われます。
http://miyazaki-jp.net/
2人目は「株式会社 大一セラム 関澤新一氏」
関澤氏の報告では、少年時代からの生い立ちの中で、支部の大先輩でもあり、父親でもある故・関澤紀一氏から受けた影響が、どのように氏の人生に根付いていったかについて語られました。
愛想がよく、大工になりたかったという少年時代。遊ぶためと嘯くように語られた学生時代の経験。そして学校を卒業し、最初に就職した家族経営の会社では、品質管理を担当。そこでは家族経営の良し悪しについて経験をすることとなります。25歳で取引先へ転職。10年の修行を経て、父親の経営する大一セラムに入社することになります。「自分に厳しく、人にやさしく」「人から受けた恩をきっちり返す」「人のために経営する」父親から学んだ帝王学は、自然と関澤氏の人生に活かされているように思えます。報告の中で「父親とはなんぞや?」という問いかけもありましたが、その思いは言葉ではなく背中を見て継承されて来たのだと感じました。
2017年に事業継承を行い現在に至りますが、先代の思いや生きざまは、新一氏の中で根付き新たな息吹となって、大一セラムの経営に生かされているのだと思います。
関澤氏の言葉・立ち居振る舞いを表現すると「誠実さ」の一言に収斂する報告でありました。
3人目は「ジュエン藤原(有) 藤原 崇氏」
藤原氏は、飲食店・不動産業を生業にしておりますが、ここまで至った経歴は、圧倒的な個性が際立ち、人を引き付ける表現しがたい魅力に富んだ報告だったと思います。
「やんちゃ」であっただろう学生時代から、現在に至る事業のきっかけを作ってくれた母親の話のどれを拾っても、誰しもが経験できるようなものではなく、傍から見れば痛快な出来事も、実際は苦難の連続だったろうと察せられました。
失敗や挫折を乗り越えてきたのは、藤原氏に胆力のなせる業でもあるのでしょうが、その行動力・学ぶ力は大いに参考にしなければいけない部分でもあります。大切なその部分を赤裸々に語ってくれたことに感銘を受けました。
現在は多店舗を展開しておりますが、折しもこのコロナ禍で苦戦を強いられることになりますが、経営努力を更に推し進め、さらなる展開を伺っているということ。
学ぶ力・やり切る胆力。氏の持ち合わせた魅力にあふれた報告となりました。
2月12日、富士宮支部2月例会が会場とオンラインのハイブリッドで行われました。
報告者は、松屋電気商会の稲原研氏が【101年目のプロポーザル~まちのでんきやさんの新たな挑戦~】と題して自身の経営について語っていただきました。

報告内容としては
1.同友会の3つの理念と同友会運動の理解を会員に話された。
2.大手ゼネコン時代の説明から、将来の人生を鑑み、脱サラをして、町の電気屋さんになった理由をお話しになり。電気屋さんと建築設計者としての「2足の草鞋状態」の中で 好きな仕事にかたよっていく苦悩をはなされ。これが自分自身が求めていたものではないと気が付き、100年周年を迎えた家業の電気屋さんの重みを徐々に理解をしていった経緯などをはなされた。
3.家業から企業にする為に自らの知識や技術 経験で地域に貢献をする意気込みをはなされ、新しい経営理念 「すすんで、考える。」と以前とことなり非常にシンプルになった経営理念を発表されていた。また、富士宮で地域にならなくてはならない企業をめざし、安心して暮らせる富士宮を作る為にあたらに従業員をやとい社会貢献され、挑戦するといっておられた。


設計等 非常に自分が好きな仕事をやってしまう事は、以前私が同じ状態におちいっていたので、非常に共感が持てた。
ただやはり人間は必然的に歳をとる。彼は、その事に気が付き、人生とむきあい、不退転の覚悟での脱サラをして、他人の責任にできない、経営者としての重要な覚悟をもって、社員や地域の皆を幸せにしていこうという考えに至る。応援したい気持ちになりました。
また、これから人を雇用すると なかなか同じ目線まで下がる事が難しくなると危惧します。
今回「すすんで、考える。」という経営理念を聞いた時にやはり。山本五十六をおもいだした人もおおかったのではないでしょうか。人との関係の中で舵をきっていくスタイルに変更した感がにじみでていた。
私は年齢は近く少し怖い人だと思っていたので、親近感がわきました。これから経営者として他人の事(社員)を主体に考えていき、非常に大変だとおもいますが、頑張っていただきたい。
(Bグループ 望月城也太)

※会場は広く席を空けて感染対策を取りながら行い、30名を超える会員が集まりました
zoomでの参加も合わせ、多くの会員がバズセッションで熱く議論を交わしました。